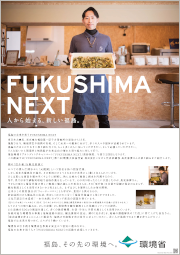設立の経緯を教えてください。
長友 海夢さん
サラリーマン時代に「何か地域の活性化に繋がるようなことをやりたい」と漠然と思っていました。それで小さい頃から縁のあった猪苗代町の地域おこし協力隊に応募し、3年間隊員として活動しました。隊員になってから、最初はボランティアとして参加し、猪苗代湖の水質保全の活動に携わるようになりました。もともと猪苗代湖は水質日本一だったけれども、私が隊員だった当時の水質のランキングは14位に落ちていました。その要因の一つが水生植物、「菱」という水草の大量の増殖。何百トンと増殖する中で、それが最後枯れて、腐敗してヘドロ状になって、水質に大きく影響を及ぼします。加えて、枯れた水草などが浜に漂着して、景観的にあまりよろしくないという、そういった地域課題もありました。観光客も多い湖ですし、他にも飲み水や農業用水など、いろんな使われ方をしています。そんな課題を改善するために、県では水生植物刈取船という船を導入して、回収・運搬して処理していました。当然、税金です。経費もかかるし手間もかかる。どうにかしたいなっていう思いが、結果的に「いなびし」という会社になりました。
現在展開している事業を簡単に教えてください。
長友 海夢さん
まず1つ目が地域の厄介ものと言われている、「菱」という水草の実を活用してお茶にしています。その売り上げの一部、お茶の1パックあたり1円が「きらめく水のふるさと磐梯」湖美来基金という猪苗代湖や裏磐梯の水環境保全の活動に使われる基金に寄付しています。
そして2つ目が(廃棄物だった菱を)商品化ができたことによって、収穫体験という観光のコンテンツになりました。菱の実を食べる、お茶を焙煎する、殻を使ったワークショップでネックレス作りなど、そんな新しい観光コンテンツですね。それと教育の要素が結構強いので、教育機関への活用、教育旅行の受け入れや会社の研修などにも体験コンテンツとして提供しています。
さらに去年から始めたのが、大学生と連携して遊休農地の活用ですね。使われなくなった町内の畑を自分たちで開墾して再生させて、その中に水草をちょっと混ぜたりとかして試験的にやっている状態です。ゆくゆくはそれを観光農園にしていこうという取り組みも始めました。

事業の発端ともなった「菱」(ひし)について教えてください。
長友 海夢さん
だいたい夏にかけて生えてくる水草で、湖面を覆い尽くすほど繁殖力が強い水生植物です。在来種なので、昔から日本にあった植物なんですけど、繁殖力が本当に強いということで、子孫繁栄や縁起物として昔は知られていたみたいです。葉はひし形っぽい形をしているのですが、家紋にひし形って結構多いじゃないですか。実はこれから来ているという話もあります。また、ひな祭りのときのひし餅。あれもひし形で縁起物ですよね。昔は結構日本人の身近な、縁起のいいものとして知られていたみたいなんですけど、今は逆に繁殖力が強すぎて、どんどん広がっていってという状態になっています。だいたい夏にかけて実が葉っぱの下に成ります。これが忍者の「まきびし」のもとと言われていて、とげが鋭いのが特徴です。お茶には、まだ実が落ちる前の、葉っぱについている状態の緑色っぽい状態のものを使っています。